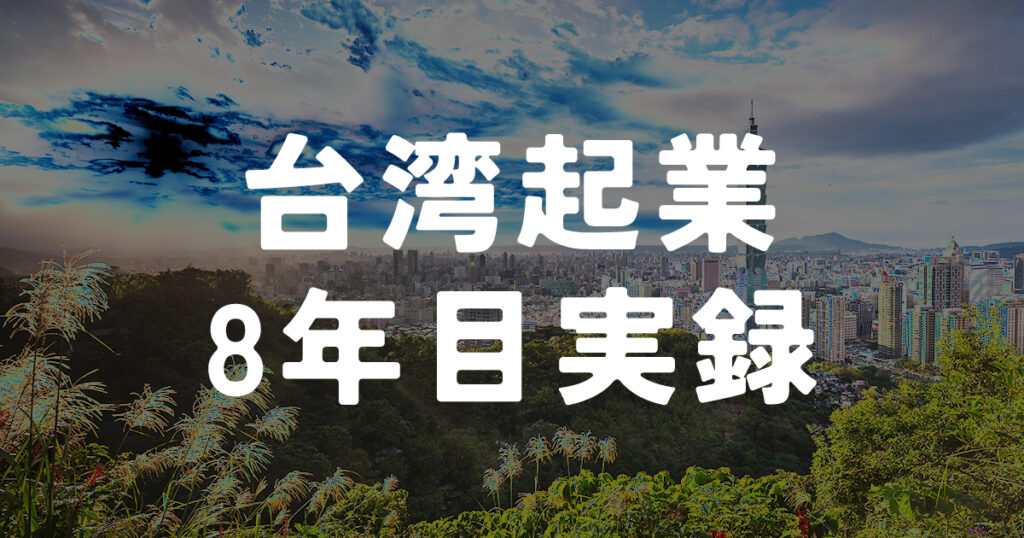こんにちは!台湾でデジタルマーケティングの会社 applemint の代表を務める佐藤(@slamdunk772) です!
今日は毎年恒例の『台湾起業〇〇年目ブログ』を書こうと思います。
毎年このブログが書ける事に感謝を申し上げます🙏🙏
知らない方のためにお伝えすると、僕は毎年1年の締めくくりに「起業〇〇年目はこんな感じでしたー」というブログを時系列で書いてます。
applemint は2025年9月に、台湾で創業して9年目を迎えるので、今回は台湾起業8年目に何が起きたかという事を時系列でお話ができればと思います!
ざっくりネタバレをすると、2024年-2025年は色んなチャンスがあったけど中々活かせず、新人も入社して社員が増えて結構内部ぐちゃぐちゃです、みたいな感じです😅
それでは台湾起業8年目のお話をしていきましょう。
Contents
2024年10月-12月:チャンス到来!でも…

この時期、僕は顧客のために 1か月で24本のショート動画を制作する という、かなり大変なプロジェクトを引き受けました。
引き受けたというより、自分で無茶な提案をして、自分で自分を追い込んだという感じです👊👊
きっかけは、ある大手企業の代表者との面談でした。その企業ではこれまでショート動画に力を入れておらず、「これはチャンスだ」と思い、僕から提案しました🖐️🖐️
参考までに説明すると、台湾では大手広告代理店はショート動画を避ける傾向があります。
大手広告代理店にとって、ショート動画は細かな作業が多く、スタッフも複数必要になる割に利益が少ないので、そもそも提案したがりません。
実際、ショート動画を作るには撮影担当、出演者、企画や分析担当など、最低でも3人は必要です。
大手広告代理店の人件費ベースでショート動画を見積もると、平気で数十万円になります。
しかしその価格では競争力がありません。
けれども安くしたくないし、作っても結果が出る可能性は低いわけです。
その結果、ショート動画の重要性は理解しつつ、広告用に月1本納品する程度にとどまっているケースが多いです。
ここに目をつけた僕らは、applemint の少人数で機動力がある強みを活かし、クライアントにショート動画を提案しました。
さらに僕自身、2024年の夏にアップした数本のショート動画がそれなりの再生数を稼ぎ、中には40万回以上再生されたものもありました。
その経験から、視聴回数を伸ばすコツを理解していたので、そのノウハウを提案書に盛り込みました。
結果として、かなり説得力のある提案になったと思います。
顧客用のショート動画の難しさ

ただ、いざ蓋を開けてみると、顧客向けに「視聴回数を稼ぐ」ことを目的としたショート動画は思ったようにうまくいきませんでした。
もし僕が純粋に「バズ」を狙った動画を企画すれば、それなりに再生数を稼げた自信はあります。
けれども顧客は僕らのショート動画にお金を払っている以上、当然そこには商品のPR要素を求めてきます。
商品のPRを盛り込みつつ、30秒程度のショート動画でバズを狙うのがいかに難しいか、このとき痛感しました。
ちなみに、僕の持論としてショート動画をバズらせるコツは「マーケティングの3Cを意識しながら、トレンドと人々の欲求に合わせること」です。
例えば、僕は「日本人」という特性を活かして中国語で日本の話をすると、それだけで説得力があり「見る理由」になります。
また、トレンドを意識することも重要です。
例えば台風が来たタイミングで「台風時の日本と台湾の対応の違い」といったネタを出すと、過去の経験上、再生数は比較的伸びやすいです。
さらに、人々が普遍的に関心を持つテーマは多くの場合「三大欲求」に関わるもので、恋愛、食事、健康といった話題は、安定して視聴数を稼げるケースが多いです。
ただし、これらの要素を顧客の商品PRと組み合わせて再生数を狙うのが難しいって話です。
アイデア出しのためにAIも活用しましたし、そのアイデアに沿って撮影した動画もいくつかありましたが、なかなか成果にはつながりませんでした。
結果的に、このプロジェクトは長く続かず、せっかくの機会だったのに半年で終了してしまいました。
今回の経験を通じて、「チャンスを掴むためには日頃から準備をしておくこと」がいかに大切かを改めて痛感しました。
あれから一年経ち、この時の経験もあり、ショート動画はかなりパワーアップできました。
2025年1月-3月:醤油への興味を体現

2025年、以前から興味を持っていた「醤油」について本格的に取り組みたいと思い、2〜3月に職人醤油さんの本社(前橋)を訪問しました💨💨
そもそものきっかけは、2024年に雑誌で醤油特集を読んだことです。
それまで僕は醤油についてまったくの素人で、種類があることすら知りませんでした。
しかし、その特集を通じて「醤油にはさまざまな種類や特徴があり、料理に合わせて使い分けることで味が大きく変わる」ということを初めて知りました。
試しに職人醤油さんのお店で「アボカドに合う」と紹介されていた醤油を使ってアボカドを食べたら、味が本当にびっくりするぐらい違って、それ以来ますます醤油に興味を持つようになりました。
訪問の話に戻ると、僕は2024年末に思い切って職人醤油さんに連絡を取り、2025年2〜3月に本社を訪問することにしました。
そこで代表の高橋さんとお会いし、意気投合し、その後4月には高橋さんが実際に台湾に来てくださり、話が一気に進んでいきました。
来年、2026年にはどこかのタイミングで「醤油のテイスティングイベント」を台北で開催しようと考えています。
2025年の初めは、新しく見つけた興味に対していろいろと「種まき」をしている時期でした。
加えて、この時期にコンテンツ担当スタッフが1名入社しました。
このときはまだ知る由もありませんでしたが、実はこの頃から僕らの内部では少しずつ綻びが出始めていました。
2025年4月-6月:新人の入社

この時期の一番のハイライトは、新人スタッフの入社でした。
2名のスタッフが applemint に加わりました。本来なら売上や財務状況を考えると1名でも十分だったのですが、そのうちの1人は台湾で起業を志すほど熱意のある人物で、急遽受け入れることにしました。
結果的に、彼には後々とても助けられていて、本当に入社してもらってよかったと思っています。
人材採用については様々な考え方がありますが、僕の意見は「常に1〜2名分の扉は開けておき、いい人材が来たら無理をしてでも入れるべき」というものです。(僕らのような中小企業に優秀な人材が来ることなんて滅多にないんですけどね…😅)
優秀な人材は、結局1人で1人以上の働きをします。
普通、中小企業の規模だと財務的に余裕がなく、ポジションが空いたら人を採用するのが一般的ですが、これでは辞めて次のスタッフが入るまでに常にギャップが生まれ、品質が落ちます。
僕はこの時に、ポジションが空いたら採用する考えを改めました。
だからこそ、自分に自信がある人は、入りたい会社にポジションが空いていなくても応募してみることをおすすめします。(ただし大企業以外では、高すぎる給与を要求したら当然落とされますけどね😅)
僕のような考え方の経営者は確実にいるので、チャンスはあるはずです。
入社した2人のスタッフはどちらもとても素直で、よく話を聞いてくれる人たちでした。
会社に対して理解も示し、特に問題はありません。
ところが僕はその状況にあぐらをかき、「台湾は海外である」という前提をすっかり忘れてしまい、人事や管理職として当然やるべき仕事を軽視してしまいました。
その結果、問題が起きることになります。
2025年7月-9月:地獄の出張と人事でてんやわんや

ここ3か月ほどは出張が続き、仕事も溜まり、久しぶりに土日までバリバリ働く日々が続いていました。
7月には3週間日本に滞在し、8月末には2泊3日という弾丸スケジュールで東京に出張することもありました。
忙しいのはありがたいことですが、外にばかり目を向けていると、内部のガバナンスや会社の標準化が疎かになることがあります。実際、この時期にスタッフから給与や人事について説明を求められる場面がありました。
詳しく知りたい方は有料メルマガ「applemint lab」をご覧いただきたいのですが、海外では給与や人事に関する要求は決して珍しいことではありません。
僕が初めてこうした経験をしたのは、起業から3年目です。
当時、某スタッフが、後から入ったスタッフより給与が低いことを知り、その件について説明を求められたのが最初でした。
以来、きちんと説明できるよう準備をするようにしています。
そもそもこうした不満が出てくるのは、日常的なコミュニケーション不足が原因です。この件を通じて、改めて考えさせられました。
ショート動画の件や人事の件を含め、課題にぶつかることは後から振り返ると非常に大切なことです。その渦中にいるときは最悪な気分ですが、課題を解決した時、会社は確実に一段階成長します。
従業員が何も言わないからといって準備を怠るのはただの怠慢です。日々コツコツと愚直に取り組むことの重要性を強く感じました。
同時に、現代はSNSを少し開くだけで、友人が良い会社で高い給与や手厚い福利厚生を得ていることが可視化され、転職の選択肢も無数にあります。
だからこそ、ひとつひとつの課題を腰を据えて解決するのは本当に難しい時代なんだな、とも思わされました。
ドタキャン ICU 生
ここで最後に余談を一つ。最近、僕の後輩にあたるICU卒業生から、最終面接をドタキャンされました😭
そもそも僕らのような中小企業にICU生が応募してくること自体、奇跡というか、ほとんどあり得ないと思っていたので、ドタキャンされても特別驚きはなかったのですが…
「やっぱりそうだよなー」って感じです。
ただ、この時改めて「自分の勘はよく当たるな」と思いました😅
後出しジャンケンみたいに聞こえるかもしれませんが、実は最初からその人に対して違和感を持っていました。
まず自分から応募してきたにもかかわらず、僕らの会社についてあまり調べていなかった事に疑問を持ちました。
ちなみに、こういう人は、僕らの会社では大抵アウトです。
ただ経歴は立派で、給与も高い水準を求めていなかったので、とりあえず最終面接で直接話をしてみようとは思っていました。(applemintの一次面接はオンラインです)
あと、一次面接で都合の悪そうな質問をしたときに、やたらと雄弁になっていたのも少し引っかかりました。(ちなみに、人は嘘をつくときに饒舌になると言われています…✌️)
僕が一番引っかかったのは、この方がリファラルを紹介できなかったことです。
会社はチームプレーで成り立っています。どんなに優秀でも、チームとして動けない人は採用したくありません。その考えから僕は応募者にこう聞きます。
「前の会社で、あなたの仕事ぶりを話してくれる方をご紹介いただけますか?」
経験上、会社で孤立していた人、チームプレーが苦手な人、あるいは努力をあまりしていなかった人は、この質問に対して色々と理由をつけて「紹介できません」と答える傾向があります(あくまで僕個人の意見ですが)
リファラルといっても、別に会社の上司である必要はなく、いいことを言ってくれる誰かで構いません。
僕自身であれば、これまでいた会社で肯定的なことを言ってくれる人は必ず1人はいますし、頑張った会社であれば、自信を持って僕の働きぶりを話してくれる人が何人も浮かびます。
ちなみに、僕らは実際にリファラルに連絡をしたことはありません🙇
結局この応募者は、僕らにリファラルを紹介できませんでした。この時点で僕は個人的に「怪しいな」と感じていましたが、結果的に僕の勘は当たり、最終面接をドタキャンするような人でした。
アウトにして正解だったと思います。
僕は過去にも「なんとなく怪しい」と感じた相手を見抜いたことがあります。
その人は表向きはお金を出すような素振りを見せていましたが、僕は違和感を覚えたので連絡を取らずに放置していました。
すると案の定、その方は後日会社を倒産させました。結果的に、僕の直感は当たっていたわけです。
何かの参考になるかわかりませんが、このリファラルを聞く面接の質問は、個人的に最も役立つ質問だと思っています。
2024年-2025年のまとめ

2025年は、正直かなり苦しい一年だったと思います。
期待に応えられず、外に目を向けすぎた結果、内部の課題が浮き彫りになりました。何をやっても毎年のように課題が出てくる――それが経営というものだと改めて感じています。
知り合いの中には最近、事業を売却して Exit した人もいますが、その気持ちはすごく理解できます。ただ、僕自身に Exit の意思は現時点ではありません。
まだまだやるべきことがあります。実際、これを書いている時点ですでに2026年に向けた「種まき」を始めています。来年、その種をなんとか芽吹かせたいと思っています。
以上、applemint代表・佐藤から、2024〜2025年、台湾起業8年目の振り返りでした!
applemintへのご相談やご連絡はこちらから!